山本 浩 / Hiroshi Yamamoto
1953年生まれ。東京外語大学卒業後、NHK アナウンサーを経て現職。 今まで残してきた名言は数知れず。J リーグ開幕や“マラドーナ5人抜き”を伝えたサッカー実況の第一人者。 法政大学スポーツ健康学部教授、(NHK BS1) J リーグタイムに出演し、日本プロサッカーリーグ特任理事を務めるなど多岐に渡って活躍中。また、サッカーに携わる以前はサッカーの経験はなかった。
キッカケは突然に
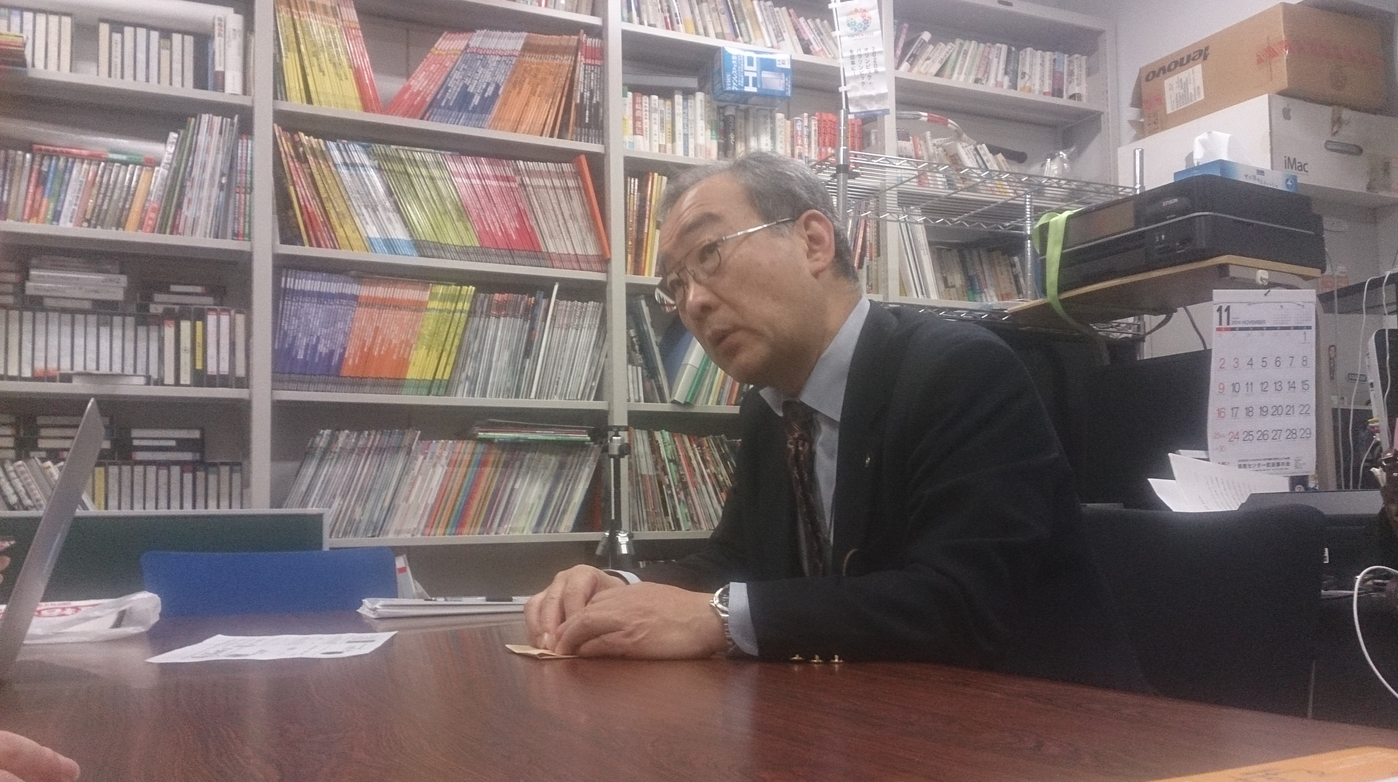
Q.元々サッカーを経験していなかったのにどういう形でサッカーと結びついたのですか?
スポーツ放送で言えば、昔は野球と相撲しか放送するイベントがなかった。野球でいえば続けてあるときには、週なかに6日試合があるでしょう。でも、サッカーは放送される試合がほとんどなかったので、放送するチャンスがあまり巡って来なかったんです。たとえば、全国向けのサッカー放送は、年に4回ぐらいしかありませんでした。そんなときには野球の実況をしている人が、サッカーの放送の為に2週間にわか勉強をしてそれをやる。で、終わったらまた野球に戻ってきちゃう。これじゃ、専門領域として成り立ちませんよね。
他のアナウンサーと同じように、僕も最初は野球の実況から入ったんですね。アナウンサーの世界というのは不思議なもので、野球の放送をして何年か経つと人によっては、「あなたは野球よりも映画の話をした方がいいね」と言われてしまったり、「料理の話をしたほうがいいね」と言われたりしながら、さまざまなジャンルに別れていくことがあります。そうした人がいったん“スポーツ” から離れてしまうと、次の任地に転勤してまたスポーツに戻るっていうことはほとんどないんです。みんな技術の積み上げだから、途中で違う道に入るとなかなか戻れないんですね。
僕がサッカーをはじめた頃には、日本がアジアの中で強くなってきた時代でした。そこで、サッカー専門のアナウンサーをつくらなければいけないという要請が生まれたのです。そんなときに野球の実況をしているアナウンサーに声をかけても、みんなあまり乗り気じゃありませんでした。「一からまたサッカーの勉強するのか」と自分に問うてみれば、15年ずっと野球の放送をやってきた人が、振り出しに戻るようなことはなかなかできませんよね。 しかも、サッカーの試合の数は少ないから、「月に2回の放送」を担当するだけでは、給料をもらうに値しないんですね。野球の世界にいて、経験豊富で周りから敬意を持ってみられていたのに、サッカーの取材に入った瞬間に、「すみません」ってパシリから始めなければいけない。経験を積んだベテランには、それまでの努力を捨てるようなこと、おいそれとできませんよ。で、「若いアナウンサーにやらせたら」という風潮が強くなった。僕がたまたま東京に勤務していたことで、「若手の山本ならサッカーやらせても、野球放送は人が沢山いるから困らないし」となった。もともと静岡や千葉、埼玉にも住んでいたからサッカーの友達も多かったのが幸いしました。
1993年になるとJリーグが始まって放送が毎週組まれるようになり、サッカーだけを専門に担当する人間が必要になってきた。ここを境に、サッカーアナウンサーが増えてきたんですよ。
見る人の側に立つ
Q.今まで山本さんはマラドーナの5人抜きやフランスW杯での初戦の時のように様々な名言や心に響く言葉を残されています。何か意識していることがあったら教えていただきたいです。
A.自分ではあまり名言だと思ってなくて。そう思われるのは、その時放送を聞いていた人の心理状態が影響したっていうのがあるんですね。長い間、日本はすごく弱かったから、なんとかして勝ちたいというような夢があった。そのときにテレビにかじりついている人やスタジアムに足を運ぶ人がどういう心情なのかなっていうのを、長い間取材していてなんとなくわかっていたんです。
例えば日本が初めてW杯(1998年フランス大会)に行ったときのことです。最初のアルゼンチン戦を放送する2時間半くらい前にスタジアムに入るんだけど、そのときにはもう日本のサポーターがスタジアムを取り巻いて並んでいたんです。でも、あのときはチケットが少なくて、たくさんのサポーターがチケットを持っていない。そういう人達がスタジアムへ入っていく僕たちの肩をたたいて「頑張ってくれ! 」って言うんです。“ 僕らの分も”ってね。それって、心に響くでしょ。めちゃめちゃ震えちゃってね。その響いたものを胸にして、ちょっとだけ言葉を出すと、同じような心情の人が日本中にいて共鳴してくれた。だから、名言を言おうとしたんじゃなくてそこにいた人達からもらった一粒一粒の言葉を乗せて伝えただけ。日本中の人が同じ心境だったから、みんなが、「あぁーっ、頑張ってくれ!」ってなっちゃった。
今、ここで仮に同じことを言っても多くの人は、「何言ってんだ」って感じだと思う。
きのうの試合(11月18日/日本対オーストラリア戦)で2−0になったときも大騒ぎしないのは、みんな勝つことにも慣れてきていて、勝つだけではなくてサッカーの内容に対して厳しくなっているから。昔は相手が強いと勝つだけで物がひっくり返るくらい大喜びしていたのに。
その時々の中で、多くの人たちの胸の内がどうなのかっていうことを感じながら言葉にしていたので、人々の心に響いたんだと思う。“見てる人の側に立たなきゃいけない”ということですね。それは凄く大事。見てる側に立たなきゃいけない。
例えば、目の前に偉い先生がきたとする。すると、司会者は偉い先生に敬語を使う。「いや、今回は大変な発見をなさいまして、その発見のおかげで日本国民が相当喜んだと思いますが」というように。このケース、口に出して敬語を使う前にいったんは、同じ場所にいる目の前の先生ではなくて、テレビで見ている側の人がもっと大事なのじゃないかと考えてみる必要がある。 同じ場所にいる先生に敬語を使うってことは「先生の方が、テレビで見ている人よりも大事だ」っていうようにもとらえられるから。あまり目の前の人にばかり敬語を使いすぎちゃいけない。同じ場所にいる人には、深い感謝の意をこめて出演料を払っているんだから(笑)。目の前の人に対して、言葉での敬意はそんなにしなくていいの。もちろん失礼のないようにするけど、テレビで見ている人が心地よく聞けるかどうかってことが大切。
放送するときには、サッカーの放送でお客さんが何を知りたがっているのかってことを考えていなきゃいけない。だから、時と場合で自分が知ってることでも質問をすることがある。スポーツの放送や一般の放送では、司会者が専門家に向かって、「1+1っていくつですか? 」って聞くことがあるんです。テレビで見ている人が「2」という答えを知らないときに、あるいは「知らないだろう」と思ったときに、しらっとして聞かなければいけないからです。つまり放送は、情報サービスだから。自分が聞きたいことだけを聞いていてはダメ。それは凄く大事。見てる側に立たなきゃいけないのね。
Q.一昔前はオフサイドの説明をされていましたが、最近ではオフサイドの説明をしていないですよね。これも時代の変化の中での”工夫”ですか?
A.そのときの時代の空気がどうなのか、時代の理解度がどうなのか。昔はカズという選手を知らない人がいたから、「三浦知良ミウラカズヨシ」って言っていた。「カズ」って口にすることは自粛していた。 それが、だんだん新聞にも出てきて、テレビにもニュースにも出てきて、みんなが何となく「カズ」ってわかってきたら、NHKも「カズ」って言うようになった。その時その時の世間の理解度を知っておくこと。例えば、20年前に「スマホ」って言ってもわからない。今はスマホがあたりまえにあるからわかるけど。言葉って先に先にと出てきてしまうもので、知らない人がいても使う人は日常生活ではどんどん使って走ってしまうことがある。でも、放送はあくまでもお客さんベースだから、“お客さんがわかった”って思ったときに使う。

だからサッカーは広がる
Q.今までで一番心動かされた試合を教えてください。
90分全体でっていうのはいろいろあって、簡単には答えが出ない。そもそも、すぐ言えるかな ?「今まで食べたうどんで一番うまかったのどれ」って聞かれたときに。(笑)それと同じように、こうした質問はなかなかやっかい。腹が減っているときにうどん食べるとうまい。同じように久しぶりに観た試合は感動することが多いかな。強いて言うならば、1986年のメキシコW杯のときの準々決勝フランス対ブラジルはすごく感動した。延長戦になって、PK戦で決まるんだけど、プラティニ (元フランス代表MF)がPKを外したり、ジーコ (元ブラジル代表MF、元日本代表監督)がPKを外したりする !(笑)とにかく全編にわたって、もの凄く質の高い試合だった。
Q.数々のスポーツの中でサッカーは特に世界・日本中に広まったスポーツだと思いますが、どんなところにサッカーの魅力があると思いますか?
サッカーというのは足を使って、ある物体をかなりのスピードとパワーで遠くに運び、狙ったところに繋いでいくスポーツなんだ。“足”っていうのは人間の体でもっとも強くものを送り出せる部位で、手よりも足の方がより強く物体にインパクトを与えることができる。それで、物体が遠くに速く飛ぶ。でも昔は、思ったところに飛ばすのは大変だと思われていたんだ。“足”って“手”に比べると、あまり器用じゃないから。足を使った練習してきた人や体の筋肉をしっかりとつくってきた人がだんだんと骨格をしっかりと動かせるようになってきた。さらにボールやシューズの質もよくなって、狙ったところにボールが行くようになった。一方で、その“ボール”は、遠くから見たときに見やすい大きさにできている。もしこのスポーツをテニスのボールサイズでやっていたら、こんなにファンは生まれなかったでしょう。遠くからは、よく見えないから。(笑)あの大きさのボールがあのスピードとパワーで動くから、見ている人にも迫力が伝わる。今の選手はテクニックも上手だし。昔はボールを蹴って2人くらいつないだと思ったら、すぐ相手に渡る。相手チームが2回パスをつないだと思ったらまた相手にとられてしまうといった具合で、つまらなかった。ところがいまでは、なにか糸でも引いてあるんじゃないかってくらいパッパッパッパッってつないでいくから、見ている人もそのボールの行方とその変化とスピードとそしてパワーになんとなく引きつけられる。偶然だと思うけど、そういう構造すべてがサッカーの魅力の背景にあるんじゃないかな。それからルールが簡単だったということも、多くの人に受け入れられた原動力。みている側が、複雑なことを考えなくてよかったっていうのもある。
昔、アテネ五輪で野球の会場に行って取材をしていた時の話し。会場には、ギリシャ人で野球を知っている人たちが何人もボランティアで観客席に入ってお客さんに説明をしている。試合の最中に、“ボーク”があった。すると、地元の観客のほとんどはボークがわからない。打ってもいないのにランナーが進塁するのを見て、観客がざわざわし出す。そこでボランティアが、ボークの説明をする。ところがその後しばらくしたら、インフィールドフライって宣告される一打があった。さすがにこれは、ボランティアの人にもわからなかったらしく、お客さんがぞろぞろ帰り始めるなんて場面に出くわした。(笑)野球ってそういった難しいルールがあるけど、サッカーはそんなのはない。そういった意味でいうとアドバンテージがあった。
選手と私たちが一体になれるスポーツ
それがサッカー
Q.最後に、山本さんが思うサッカーの持つ可能性とは?

選手と見ている側が一体になれる。それがサッカー。いまではサッカーを知っている人がたくさん生まれ、例えば、試合をテレビで観ていると、日本代表の遠藤が前線にあがっていくと、「今打たなきゃ!」なんてつぶやく人がいる。あるいは、勝ったときにすごくうれしい感情が湧くとちょうど遠藤と自分が重なることがある。極端に言えば、遠藤の指導者みたいになっちゃうこともある。応援しているサッカーは、それこそ“彼ら”がやっているんじゃなくて“自分たち”がやっているみたいに感じられる。サッカーには、そういった一体感みたいなものを引っ張り出してくる力がある。サッカーが人を虜にする。まさに自分たちがそんなシュートを打てるみたいに思い込んで、叫んだり悔しがったりする。例えば、ウサイン・ボルトが走っているときに、自分がボルトみたいに速く走っていると思う人はいない。「もっといけよ !」とか言わない。(笑)サッカーってそういうものがあって、選手とわたしたちが一体になれる。それがサッカーの魅力のひとつかな。
WorldFut インタビュアー
永井千晶、天野楓夕美、渡辺大二郎、山本奈

コメント記入欄