1992年からワシントン州立大学でスポーツマネジメントを学ぶ。
1997年に富士通川崎フットボールクラブ(現川崎フロンターレ)に採用され、ホームタウン推進室でクラブの地域密着を推進。現在は川崎フロンターレのサッカー事業部・プロモーション部長として活躍している。
アメリカで体感したスポーツビジネス
Q.プロモーション部として活躍するまでの経緯についてお聞きします。川崎フロンターレに入ったきっかけについて聞かせてください。

きっかけはタイミングですかね。僕を採用してくれたのがフロンターレだけでした(笑)。
フロンターレに入社する前はアメリカの大学に留学していて、向こうで働く選択肢もなくはなかったのだけど、アメリカではスポーツを取り巻く環境はすでに成熟、確立されている。かたや日本は、プロ野球はあるけれど、当時はどちらかというと企業スポーツの延長みたいなもの。最近は変わってきましたけどね。
アメリカ留学中の1993年に、自分自身も小学生の頃からやっていたサッカーがプロになって、Jリーグができたから、「これはまだスポーツ環境が整っていない母国、日本で勝負しよう」と帰国することにしました。ただ、Jリーグのクラブにツテなんてないから当時の全10クラブに企画書を送り、アプローチしました。結果は、7クラブは返事なしで、3クラブは手紙で『お断り』の返信をくれました。まあ、そんなに甘くないですよね。そのとき、川﨑フロンターレの前身の富士通川崎フットボールクラブがプロになるという記事をサッカーマガジンで見つけ、「これだ!」と思ってすぐアポを取り、そのときのGMに会ってもらいました。自分の行動を振り返ると超強引です(笑)。クラブ事務所に出向いて机の上にドサドサッと企画書を7つくらい並べて、『自分を採ってくれればこんなことができる』とアツく語ったのを覚えています。そうしたら、「じゃあ明日から来て」って感じですぐに決まってしまいました。まさか、そんな感じで簡単に決まると思ってなかったので、僕が「え?!明日からですか?」みたいな焦ったリアクションをとってしまいましたね(笑)。後から聞いた話ですが、ちょうど若手のスタッフを採ろうと考えてた矢先に僕からの電話が鳴ったみたいです。そう考えると実力とかではなく、完全に「タイミング」が良かったんですね。
Q.アメリカに留学されていた時に、スポーツに携わる仕事をしたいと思ったのですか?
アメリカでは、カレッジスポーツがビッグビジネスになっています。動いているバジェットは、アメフト(NFL)、バスケ(NBA)についで、三番目にカレッジフットボールが来るくらい、カレッジスポーツというのは規模が大きくステイタスもあるんです。。
僕はアメリカのワシントン州にあるワシントン州立大学でスポーツマネジメントを学んだのですが、一番の魅力は、自分の大学のチームで働かせてもらえることです。プロにもひけをとらない規模のチーム運営に身をおき、「これはオレの天職だ」と思うほど魅了されました。日常の中に、人の心を揺さぶる「非日常」の空間を創造できるってスゴいことですよね。勝ったら嬉しいし、負けたら悔しくて悲しい。喜怒哀楽を自然に表現できる場を作り出すスポーツの力に引き込まれました。それと、スポーツの素晴らしいのは、人の心や地域を「繋げる」力も持っている。ワシントン州立大学のチームは、「地域」を背負って戦っているんですね。学生だけでなく、街の人たちは、自分たちの代表が自分の代わりに戦っている感覚でいるんです。街の誇りであり、シンボルであり、街の子どもたちにとっては身近なヒーローなんです。赤の他人でも、街のチームを応援しているだけで、みんな仲間になれてしまう。そんなことがスポーツってすごいな、この世界で食っていきたいなと強く思ったきっかけです。
そんな中、日本で初めて「Jリーグ」という地域性を持ったプロスポーツが誕生しました。Jリーグがなかったら僕も日本で力を発揮できなかったし、そう考えるとやはり「タイミング」が良かったんですね。
人を幸せにする最前線
Q.プロモーションという色々な企画を仕掛けてクラブを盛り上げるという仕事の中での感じるやりがいはなんでしょうか?
やりがいは、やはり「人を笑顔に」する事ができることですね。アメリカでスポーツの本質を体感したことで、どうやったら日本の社会でスポーツを活用できるかがイメージできるようになりました。プロサッカーの興行のメインは、もちろん試合であるんですけど、試合は勝ち負けがあるので、来場された皆さんを毎回ハッピーにすることができません。J1は18クラブあり、強いと評価されるのはACLに出場できる3位くらいまでですよね。あとはもう勝ったり負けたりで、下位のチームなんかは負けばかりなのが現実です。「勝ち続ければ」だとか、「優勝すれば」だとかの「たられば」は期待してはいけません。ここはしっかり勝負事の現実を受け止めて運営することが大事なんです。
そうなってくると、必然的に「競技」以外の魅力をクラブは持ち合わせていないとなってきますよね。たとえ勝てない試合でも「スタジアムに行って楽しかった」、「このクラブを応援していてよかった」と思えるものを作り出すことが重要になってきます。これは、競技とは違い、僕たち事業スタッフの企画力、実行力と熱量で確実に生み出すことが可能な計算できる分野なんです。ただ、この国は依然として「プロスポーツは競技力だけで成り立つ」という考えが常識となっているので、それをこのフロンターレで覆してやる!というのが僕のモチベーションです。スポーツの新たな活用方法を示すことにやりがいを感じています。
Q.その中でやりがいを感じたエピソードはありますか?

1番やりがいを感じるのは、スタジアムを訪れる人の嬉しそうな表情を見たときですね。お父さん、お母さんが子どもとお揃いのユニフォームを着て試合前のフロンパーク(スタジアム前のイベント広場)で楽しく食事やアトラクションに参加している姿を見ると、毎回本当に感動します。もっともっと頑張ってみんなを幸せにしたいと強く思いますよ。
自分たちがプロモーションを仕掛けて、さらにその日の試合に勝てば、みんなが超ハッピーになる。みんなの笑顔をつくれる。どんな仕事であっても、究極は「だれかの為に役に立ちたい、誰かの笑顔を作りたい」って思いながら仕事していると思います。花屋さんだろうが、肉屋さんだろうが、ケーキ屋さんだろうが、みんなそうですよね。僕の仕事はそれがよりダイレクトに伝わってくる。すごく重要なポジションだし、それはすごいやりがいでもあります。
Q.やったことが実際に見えるというのが、天野さん自身が地域密着にこだわる理由でもあるんでしょうか?
そうですね。現在Jリーグクラブは、J3までいれると51クラブにもなります。これらJクラブの存在意義は、「自分たちの街の人を未来永劫幸せにする、笑顔にする」ことです。幸せにしたり、笑顔をつくれたりするのは、クラブが地域から享受されていなければ絶対にできません。目的達成のためには、地域に愛されていなければ始まらないのです。
それなので、「地域密着」というのは別に特別なことではなく、目的達成のためには当たり前のことなんですね。よく「地域密着してますね」とか言われますけど、僕の感覚からすると「1+1は2ですよね」と言われている感じがします。
前例を作る
Q.今まで数多くのイベントや企画を作り上げてきたと思いますが、企画をつくる上で、意識している事、大事にしている事を教えてください。
それはね、イベントでジャニーズは呼ばない(笑)。つまり、そのものにチカラがあってそれでお客さんを呼んでも意味がないということです。
イベントとかプロモーションをやる上で大事にしている事が5つあります。1つ目は「地域性」、イベントの中に必ず地域性がある事。仕掛けることで、川崎っていいなっ、川崎に住んでてよかったなと、ちょっとでも地域を意識できる要素を入れ込むことです。
2つ目は「話題性」。1つ目の要素である地域性はどうしてもローカル色が強いから地味になりがちです。なので、そこをいかに工夫して話題性を生み出すかを常に考えています。
3つ目はイベントの中での「社会性、公共性」を作るつくることです。我々がやるイベントとかプロモーションがフロンターレのためだけじゃなくて、他の人のためにもなっている仕掛けを意識しています。4つ目が「継続性」です。単発では意味がありませんので。最後はこれらを「低予算」でやる営業力や交渉力。僕はこの5つのチェック項目を常に意識しながらやってます。
例えば、今までに手がけたものの中で「いっしょにお風呂ンターレ」というイベントがありますが、あれは12月~2月というクラブの露出が減るオフ期間にどうやってクラブの存在価値をアピールするかを考えて展開しました。フロンターレらしさを失うことなく、地元銭湯利用を促進するプロモーションは、まさしく上記の5つのチェックポイントを意識しながら企画を組み立てていきました。2回、3回と同じ企画を繰り返しても話題性が乏しくなるので、毎年、切り口をかえて「テロマエ・ロマエ」と組んだり、NHKの「オフロスキー」とコラボして展開しましたね。企画は「絵の具」と一緒で、既存の「色」と「色」を調合して「新しい色」を生み出すことだと思います。0から生まれるものではなくて、この世の中で存在するものを繋いだり、くっつけたりしながら、切り口や見せ方を工夫してオリジナルのものを生み出す。僕はそうやって企画を立案してます。
Q.フロンターレでのプロモーションを通して、川崎という地域をこれからどのようにしていきたいですか?
まずはスタジアムを川崎市民を中心としたお客さんでいっぱいにすることです。ホームスタジアムの収容率はクラブへの愛情、需要のバロメーターですから。
僕は地域とは「声援」だけではなく、「支援」もしてもらえる関係をつくることが大事だと思っています。誤解しないできいてほしいのですが、街で「がんばってね」といわれるのは、すごく嬉しいです。ただ、「がんばれ」って誰でもいえると思うんですよ。変な話、「がんばれ」って思ってなくても言えますよね。僕らプロサッカークラブは、クラブを経営、運営していかなければいけないので、いかに「このクラブを支えたい」と思い、行動を起こしてもらえるか。それはファンクラブ入会でもチケット購入でも看板掲出いいんです。また金銭だけの問題でなく、ボランティアさんのように「労力」でクラブを支えてもらってもいいんです。声援と合わせ、支援してもらえる、支援したいと思われる関係を構築することが大事だと思います。
Q.川崎での最終的なゴールはありますか?
まずは、川崎市民144万人が後援会会員になることですね。川崎市民なのだから川崎フロンターレを応援することがごく自然、当たり前という状況まで持っていきたいです。
「そんなことできない」と思うのは簡単ですが、僕は決して不可能なことではないと真剣に思って取り組んでます。
喜怒哀楽
Q.今の仕事を含めサッカーに携わっていて良かったなと思える瞬間はありますか?
年をとってくると「喜怒哀楽」を表現できる環境、状況が少なくなってきます。学生のときは、運動会や学芸会、文化祭などみんなで喜怒哀楽を共有する機会がありますが、社会人になると、喜怒哀楽の感情露出を抑制しながら日々過ごすことをことが多くなります。日本の社会は特にそうかもしれませんね。でもサッカークラブ運営を仕事にしていると、試合に勝てば選手やサポーターや地域の皆さんと喜びを共有できるし、負けたらご飯が喉が通らないほど落ち込むこともあります。大人になっても感情の起伏がサッカーによって形成されることで人間らしく生きているなと感じます。
ヒューマンライン
Q.天野さんの考えるサッカーの可能性とは?
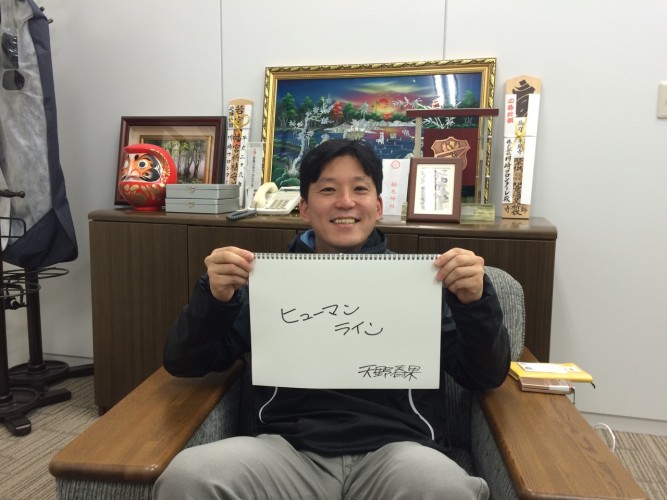
”ヒューマンライン”
これは僕がつくった造語ですが、スポーツは「ヒューマンライン」だと思うんです。スポーツは水とか空気とか、人間が生きていくうえで必要な「ライフライン」ではないですよね?スポーツを見なくてもやらなくても人間は生きていくことが出来ますから。
でも、人間が人間らしく生きるためには絶対に必要なもの=「ヒューマンライン」ではあると思うんです。音楽や芸術、芸能や食事などもスポーツと同じ「ヒューマンライン」ですよね。他の動物にはあたえられず、人間だけが神様からあたえられた「生きるうえでの楽しみ」だと思います。
ただ、日本の中でスポーツが「ヒューマンライン」として確立されているかというと、まだまだですよね。上記した音楽や芸術などは「文化」としてしっかりと日本の中でも確立されているのに、それらと比べれば、スポーツはやはりまだまだ「文化」に成りえていません。逆を返せば、これから確立していける未開発な分野です。だからこそ可能性があるし、開拓者として「築いていくぞ」とモチベーションも高く保てます。
僕は大学の先生ではなく、「実践者」です。スポーツ文化を語るのではなく、フロンターレの場で自分のアイデアを形にしてこれからも前に進んでいきたいと思います。
天野春果さんありがとうございました。

Facebookコメント欄