松崎 英吾 / Eigo Matsuzaki
日本ブラインドサッカー協会事務局長。国際基督教大学卒。1979年生まれ/2児の父。
学生時代に、偶然に出会ったブラインドサッカーに衝撃を受け、深く関わるようになる。大学卒業後は、出版社に勤務。業務の傍らブラインドサッカーの手伝いを続けていたが、「ブラインドサッカーを通じて社会を変えたい」との想いで、日本視覚障害者サッカー協会(現・日本ブラインドサッカー協会)の事務局長に就任。スポーツに関わる障がい者が社会で力を発揮できていない現状に疑問を抱き、障がい者雇用についても啓発を続ける。サステナビリティがあり、事業型で非営利という新しい形のスポーツ組織を模索しながら築いている。
ブラインドサッカーとは
ブラインドサッカーとは、全盲の選手がプレーします。
ブラインドサッカーは、通常、情報の8割を得ているという視覚を閉じた状態でプレーします。技術だけではなく、視覚障害者と健常者が力を合わせてプレーするため、「音」と「声のコミュニケーション」が重要です。(ブラインドサッカー協会HPより引用)
ブラインドサッカーに関する動画はコチラ↓
目から鱗がおちた体験
Qブラインドサッカーとの出会うことになったきっかけはなんですか?
大学三年生の夏にインターンとしての仕事を通して出会いました。
大学三年生の夏って、就職に対する漠とした不安や、就職した先で何をやるのかとか、何かチャレンジをするかとか、結局大きなうねりに飲み込まれていくようなものに対する反発心というか、僕にもあったんですね。その時自分では、夢があって、ジャーナリストになりたかったんです。そのためにアクションしていきたくて、アルバイトじゃなく、インターン先を探していました。何かないのかなって、本当にもがきながら探していたんですね。
その時に見つけたのが、個人で報道活動しているの方の事務所でした。インターン募集中ではなかったんですよ。そこをがんばって連絡をとっていたら受け入れてくださって。
Qそのインターン先を通してブラインドサッカーと出会ったんですね?
そうですね。 当時、ブラインドサッカーのことを 「視覚障害者がやるサッカーみたいな競技」だと思っていました。そんなに障害に理解があったわけではないし、むしろ障害者に対する反発心みたいなのもあったので、できれば僕は付き合いたくない存在だったんです。当然、視覚障害者がやるサッカーと聞いて喜んで行こう、面白そうと思ったわけでは全くなかったです。
京都の奥の方のゴルフ場で行われた合宿に行ったんですけど、集合から僕はどうしていいかわからなくて。
視覚障害者を、初めて見るし、初めて会うし、初めて接するし。隣で同じ年ぐらいの男性が、4、5人を、ずらっとひきつれているのに、僕はそこで誰も助けてないわけですよ。居心地の悪さも感じていましたし、自分がどうしていいかわからない。来なきゃよかったなとも思いました。でも、ピッチに立って一緒にプレーをし始めたら、そういうのがどんどん崩れていった。いわゆる合宿のサポートとしてボール拾いしたり、パスの相手をしたりという形ですね。練習以外でもお風呂に一緒に入ったり、夜いろんな話をしたり、これだけ偏見を持っていた自分が、どんどん目から鱗な状態が体感できて、「あ、僕ですらこんなに理解できる。友達みたいに変わっていくんだな」と思いました。
サッカーというスポーツを通してピッチの上で彼らと交流したっていうことが大きかったと思います。
Q合宿が終わった後もブラインドサッカーに関ろうと思っていたんですか?
合宿での出会い方はすごくポジティブだったんです。関東に戻ってきたときに一緒に合宿でやった視覚障害者の関東在住の人たちから、「練習場所がない」という話を聞いて。練習場所がない人たちがなんかもどかしくて。だったら「お手伝いできることがあったら手伝いますよ」という形で、練習場所を探したりとか確保したりだとか、それがきっかけブラインドサッカーに関わっていました。
パスが繋がるってとても気持ちのいいこと
Qブラインドサッカーの魅力とは何ですか?
ブラインドサッカーは視覚障害者ためのスポーツであると同時に、誰もが参加しやすいスポーツであるっていうことですね。
目を隠せばだれでもできる事もそうなんですけど、眼っていう感覚自体は、私たちは普段すごく頼りにしている。その視力が奪われた時にどれくらいの動きができるだろうかというのを、実際の選手が見せてくれる『プレーのギャップの大きさ』っていうところが、「私たちは関係ないかな」と思っている人たちに対しても、訴求できる部分と思っています。
それを体験するのに、”ボール1つとアイマスクさえあれば、なくても目をつむれば体験できる。そのユニバーサルであることが、ブラインドサッカーの魅力の一つであると思いますね。
もう一つ挙げると、視覚障害当事者、競技者にとってですね。多くの視覚障害者スポーツがあって、その中でも私たちはかなり特徴的なんです。視覚障害者スポーツのルールの発想というのが、安全であることなので、攻撃と守備を分ける形や、攻撃と守備が入り乱れない形というのが、基本にある。。ブラインドサッカーは攻守が入り乱れる形なんです。それがゆえに「危ないんじゃない」という声もいただくんですけど、でも、そういうスポーツが過去に無かったですし、すごくエキサイティングです。体と体のぶつかり合いっていうことが、すごくこのスポーツの魅力なんですね。もちろん安全管理はしつつ、その魅力を失わずにいることが選手たちにとって、メリットになっているんだろうなという風に思いますね。
Qブラインドサッカーと一般的なサッカーとの違いはなんですか?
僕ら目が見えていて五体満足といわれる存在であると、当たり前のことが当たり前すぎて分からないことが沢山あるんですよ。
「コミュニケーション」と一口に言っても、みんな「自分は大丈夫だ」と内心では思っているはずです。でも、見えない状態でお互い理解し合いながら、頼り合いながら、信頼しながらゴールを奪う、守るというブラインドサッカーのゲームをしていると、すごくいろんなものに気づくことができるんです。
サッカーで「しっかり声出せ」とか、「コミュニケーションとっていこう」と言いますよね。ブラインドサッカー自体がハンデがあって、支えられなきゃいけないスポーツと捉えられがちなんですけど、健常者の僕らこそ、そこから学べることがあるんですよね。
サッカーとブラインドサッカーは別物ではあるんですけど、サッカーやフットサルをやっている人がブラインドサッカーから学べることが多いんですよ。
僕はサッカーの魅力をブラインドサッカーやって初めてわかった気がします。サッカーって素晴らしいなと思えたのは、A代表やJリーグの試合を見たからではないんです。、ブラインドサッカーのプレーを見て、そう思えました。
もちろん「チームワークが大事」とは言う訳ですけど、言葉でそれを言って、どの深さで理解できるかというのは、人それぞれ全然別物だと思うんですよね。
理解、深さもそうだし、例えば、ブラインドサッカーは1時間くらいパス続けられちゃうんですよ。パスが繋がるってすごく気持ちがいいことなんです。ちゃんとパスを受けとってくれて、お互い声かけあって、ここだって分かるみたいな。
蹴ればボールはそっちに行って止められる訳なんですよ。そのこと自体がすごく価値があることなんです。
これは僕の原体験で、先天的な視覚障害者の小学校3年生の女の子が初めて蹴った瞬間に立ち会ったんです。それまでその子は自覚的に蹴ったことがなかったんですよね。
遠いどこかの国でなく、この日本でもボールを『蹴る』ことが当たり前じゃない環境があって、ボールを蹴ってるその子の喜んでいる姿を見た時は、『蹴る』って僕らの仕事をしていく上では、「じゃあそれがどう生きる力に影響を及ぼすのか?」とか考えちゃうんです。単純に『蹴る』って楽しいんだなってことを僕は彼女から学びました。
一緒に成長してきた 一緒に頑張ってきた仲間
Q.代表選手の方とかと直接お話しする機会はありますか?またそのときにどんな話をしていますか?
サッカーの戦術については、できるだけ話をしないようにしていますね。
それは代表チーム部という組織がある以上、監督を任命して、スタッフを任命して、世界で戦ってもらう以上、僕がこういうサッカーやるべきじゃないということは言うべきじゃないと思うんですね。
それ以上にしっかりと勉強して分析して、どういうプロセスを経て代表を世界で勝たせようかって考えている人がいて。
僕は120%彼らを信頼しているので、僕から戦術はこうあるべきだとかいう話はほとんどしないですね。
ただ同時に今の代表の選手たちは僕が出会ったころの、このスポーツに出会った時の仲間ですし、僕は地域でチームもやっていたので、その時のチームメイトもいるので、普通の友達でもあるんですよね。
だからもちろんいろんな話もしますけど、戦術の話っていうのはあんまりしないですね。
Q松崎さんが現在行われている仕事の話もしますか?
しますよ。やっぱり選手も気にはなってると思いますね。
協会がこれからどうしていくのか、今代表選手と世界を目指していくなかで、もっと世界で戦っていくためにはもっと成長したいし、環境だって変えていかないといけないと考えた時に、協会が今のままでいいやって思ったら、彼らだけに負担を強いてしまうことになる。やっぱり彼らと共に戦っているんだなっていうのは協会としてもしっかり感じ取るし、彼らが何に困っていてどうしたいのか、個人個人でいくと転職したいのかということは話をするようにしているので、環境面の整備もそうですし、協会はもっともっと彼らのためにできることがあると思ってるので、情報収集みたいなこともします。
Q松崎さんと日本代表選手は関係性がとてもよいイメージを受けます。
僕が今の代表とはすごく長い時間を過ごしてきて、同世代でもあります。僕らの苦労も彼らは分かっているし、彼らの苦労を僕もわかっているし、今の代表の選手たちとはやっぱりすごい信頼関係があると思っています。だから僕がちょっと変なこと考えていたりすると彼らは意見を言ってくれる。ちょっと特別な関係かもしれないですけどね。
5年経って代表のメンバーが入れ替わったら多分、そういう状態じゃなくなると思うし、意外と僕が影響力あるんだなということを組織の中で感じます。立場を知った途端になんかちょっとよそよそしい態度になる20歳とかもいるので、そういう意味では今はちょっと特別な関係です。今の代表とは、昔から一緒にやっていたし、若い頃から知っていますし、お互いだめだった頃もよくわかっています。
一緒に成長してきた、一緒に頑張ってきたっていう仲間です。
すごい!!で社会を変える
Q 最後に松崎さんの今後のビジョンを教えてください
僕らは競技団体なので視覚障害当事者がプレーをしていくこと、それは草の根であり、日本代表のアスリートであるっていうのを統括するところはすごく大事なミッションなんです。
役割なんです。「混ざり合う社会」というものを掲げている以上、身の回りだけでやっても混ざり合う社会は実現できないと僕らは思っているんですね。
たぶん皆さんもブラインドサッカー日本代表が世界で勝てば、もっと有名になって、もっとうまくいくんじゃないかと思っているかもしれませんが、僕はそれは嘘だと思っています。
他の障害者スポーツや他のマイナースポーツを見ても、勝ったら一時的にはメデイアに出るけど、認知度は全然上がらないし、一時的に出ても全くじゃないけど、意味は非常に低いんですね。
勝つのだけではうまく回らないものっていっぱいあるはずなのに、スポーツで競技をやっていると勝てば何とかなるって思っちゃうんですよね。
(ブラインドサッカー協会では同時に混ざり合う社会というのを掲げている )
僕はそれはちょっと違うんじゃないって思いをもっていて、混ざり合う社会っていうものを掲げた時に勝っても負けても混ざり合う社会って実現できない。
それはやっぱり実は混ざり合うためには目が見えている人が、いわゆる障害がないといわれている人たちがどういう眼差しで障害者を見るかがすごく大事というわけですね。
それを広げていくには、見えている人つまり障害がないといわれている人にいかに体験してもらって、自分事としてとらえてもらうかが大事。障害者がかわいそうな存在や何もできないマイナスな存在だけでなく、一つの個性のでこぼことして障害があってもこれはできる、これは普通の人よりも得意っていうのはやっぱりあるわけですよね。
そういう個性の「でこぼこ」としてとらえてもらって、それが社会としては「豊かさ」や「より良い社会」につながっていくという眼差しに変えていくというのが大事だと思っている。だから、見える人向けの事業っていうのを片手間ではなくて、しっかりと行っていく。そういうことを意識して、「すごい!」で社会を変えていきたいと考えています。
松崎さんありがとうございました。

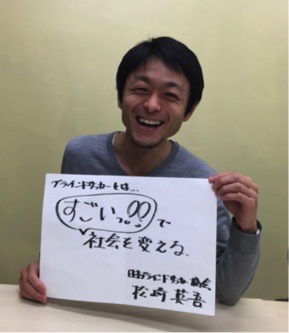
Facebookコメント欄